更新日:|登録日:
更新日:|登録日:
こちらのページでは、先天性の胸部や心臓の病気や出生前診断の方法などを紹介していきます。
心臓や胸部の異常は出生後すぐに循環器や呼吸に影響するため、妊婦健診の超音波(エコー)検査で入念にチェックされます。
妊婦健診の超音波検査で、心拍数や心臓の位置などをチェックしていきます。その中で胸部や心臓およびその周辺の異常が疑われた場合は、さらに明瞭な画像と画像解読に優れた医師による精密超音波検査やMRI検査で診ていきます。MRIは骨に囲まれた部分でもクリアな画像になるため、肺の異常に関して有効な手段です。
ただし、先天的な心疾患は、一般的な妊婦健診の超音波検査で見つけにくいものもあり、4つの部屋がきちんとあるような心臓異常(大血管転換症や一部の両大血管右室起始症やファロー四徴症など)もあります。
また赤ちゃんの心臓は1分間に150~160回も打っていて胎動もあるためいつも同じ方向から観察できないため、心臓異常の診断はどうしても妊娠後半期にされることが多いです。お腹の赤ちゃんの健康状態が心配な人は、精密超音波検査を受けるのも1つの方法です。
胎児が成長するとともに心拍数も変化します。一番心拍数が多いのが妊娠9週ごろで170~180回/分ほどですが、その後少し下がり、妊娠期間を通じて150~160回/分が正常範囲と見なされています。
心拍数の異常が問題になるのは、継続的に180回/分を超える状態(頻脈)や、130回/分未満の状態(徐脈)が続くとき、急に速くなったり心拍数が安定しなかったりする場合や不整脈があるケースです。
頻脈の胎児は「絨毛膜羊膜炎」などの子宮内感染や赤ちゃんの貧血が疑われる場合もあります。また徐脈の場合は「不整脈」や「心不全」などが疑われます。心臓にブロックと呼ばれる不整脈がある時には、60-70回/分という徐脈がずっと続いているにもかかわらず、赤ちゃんが普通に育っていて元気に動いていることがあります。このような特殊な場合もあるため、循環器の専門家に診てもらうことが必要です。
ただし妊娠中には一時的に徐脈になることもあるので、医師の指示に従いましょう。
妊婦健診の超音波検査では、必ず胎児の心拍をチェックします。必ずしも心拍数を確認するわけではありませんが、徐脈や頻脈は心拍チェックのときに疑われることがあります。
妊娠12週目以降であれば「ドップラ聴診器」と呼ばれる機器で確認されることもあります。
また出産が近くなると、胎児の心拍数や胎動、子宮収縮を同時に検査できるノンストレステストを受けることがあります。
心拍数の異常はさまざまなケースが考えられるため、担当医師のアドバイスに従うことになります。
生まれつき肺動脈が狭くなっている病気が肺動脈狭窄です。先天的な心疾患の約10%を占めると言われています。心臓から肺に流れる血管が狭くなっているため、血液を送るのに通常の人以上に労力が必要となります。
軽度の場合は自覚症状すらありませんが、動脈の狭窄レベルが中度以上の場合は、息切れや母乳・ミルクを飲まない、チアノーゼ症が起こりやすい、その他にも心臓に負担がかかるために心不全の恐れもあります。他の心臓の形態異常を伴っている人もいます。
画像診断の専門家のいる医療機関で行う精密超音波検査で、右室からの流出路の大きさで肺動脈狭窄が疑われると診断されることがあります。しかし狭窄の程度にもよるため、すべてが診断できるわけではありません。
肺動脈狭窄の治療は、軽度の場合は病状の経過を観察するケースがほとんどです。中度以上の場合は、お子さんの成長に合わせてカテーテル治療を行ったり、外科手術で狭い弁や血管を拡げたりする方法がとられます。
大動脈と肺動脈の2つの大血管の大部分が、右心室から起始する心奇形を両大血管右室起始症(だいりょうけっかんうしつきししょう)と言います。そのほとんどに心室中隔欠損が見られます。
心室中隔の穴と大血管との位置や大血管の太さ、心室の大きさ、合併する病気など病態が幅広いのが特徴。2つの大血管が、それぞれ50%以上右室から起始することが定義づけられています。病態によって、肺高血圧症やチアノーゼなどの症状が起こります。後述のファロー四徴症との区別が難しい場合もありますし、心室中隔欠損という診断だけがなされることもあります。診断名が突然変わったりすることがありますが、病名よりも血液循環がどうなっているかということのほうが大切です。
両大血管右室起始症は、心臓の軸や心室と大動脈とのつながりの異常などから精密超音波検査で確認できることあります。
両大血管右室起始症は外科的手術で治療しますが、その病態によって異なります。例えば乳児期に肺血流が多い場合は心不全を防ぐ「肺動脈絞扼術」、反対に肺血流が少ない場合であれば「体動脈肺動脈短絡術」が必要です。
その後、ある程度成長してから病態に合う手術が行われます。
左心低形成症候群とは、左心室が通常より小さい先天性心疾患です。左心室の入口と出口である大動脈弁の閉鎖(または狭窄)と、僧帽弁閉鎖(または狭窄)が特徴です。左心室の低形成の程度や大動脈弁と僧帽弁の状態にもよりますが、治療なしに新生児期を乗り切ることは難しい重篤な先天低心疾患とされています。
出生後は全身性のチアノーゼや低体温、脈が早い、肝臓が腫れるなどの状態になり、動脈管開存を維持しなければショック状態に陥ります。
精密超音波検査で左心低形成症候群が診断されるケースが増えていますが、すべてではありません。妊娠経過や胎児の成長が正常であることが多いため、注意深く心臓の画像診断をする必要があるからです。
左心低形成症候群は、体と肺の血流のバランスを管理しながら外科手術の治療を行います。手術は新生児時期に第一期手術の「ノルウッド術」を行い、生後6カ月頃に「グレン手術」を実施。2歳前後に第三期の「フォンタン手術」を行います。強心剤や利尿剤、アスピリンなどの服用も必要です。
三尖弁(さんせんべん)とは、右心房と右心室の間にある弁のことで、血液が逆流しないように働いています。三尖弁閉鎖症とは、この弁が先天的に閉じられている疾患で、全身からかえってきた血液は、心房中隔欠損孔か卵円孔を通って左心房へ流れてしまいます。
酸素の少ない静脈血が流れ込むため、全身へ流れる酸素含有量が低下してチアノーゼの症状が出るのが特徴です。また、肺へ流れる血液量が多くなるために肺や心臓に負担がかかる場合もあります。
三尖弁閉鎖症は、家族や親戚内で発生したり染色体異常を伴い発生したりする例もありますが、はっきりとした原因はわかっていません。
三尖弁閉鎖症は、右室低形成や心房中隔欠損症などの別の心疾患と合併していることがあり、妊婦健診の一般超音波検査や専門家による精密超音波検査でわかることがあります。
胎児の心臓がある程度成長する妊娠後期に判明しやすいですが、すべての三尖弁閉鎖症が判明するわけではありません。
出生後、肺に流れる血液を確保するために「プロスタグランジン」という薬を点滴します。その後、動脈管のかわりに「シャント手術」を実施。逆に肺へ血流が多く流れ過ぎている場合は「肺動脈絞扼術」を行います。
症状によってその後も段階的な手術が必要になりますが、最終的にはチアノーゼ症状をなくすために「フォンタン手術」を目指すことになります。
心臓の右心室と左心室の間の壁を心室中隔と呼びます。この壁に穴があいている病気が「心室中隔欠損症」で、右心房と左心室の間の壁に穴があいている病気が「心房中隔欠損症」です。「心室中隔欠損症」は生まれつきの全心疾患のうち50~60%を占めており、他の心疾患と合併しているケースもあります。
妊娠後期の超音波検査、あるいは出生前診断の精密超音波検査で発見できるケースもありますが、中隔の穴が小さい場合は確認できないケースもあります。
フランスのファロー医師によって報告された先天性の心疾患です。チアノーゼを起こしやすく、「心室中隔欠損・大動脈騎乗・肺動脈狭窄・右室肥大」という4つの病態を持つのが特徴です。染色体22番の22q11.2欠失症候群やトリソミーなどの染色体異常の合併が見られるケースもあります。
ファロー四徴症は心臓の軸や大きさ、流出路などが詳しく見られる精密超音波検査で診断されることがあり、生後6カ月から2歳頃までに、外科的手術で根治を目指せます。
横隔膜ヘルニアとは、先天的に横隔膜に孔が開いている状態のことです。胸とお腹を隔てる横隔膜に孔があるため、胃や肝臓、脾臓などが胸部に入り込んで肺を圧迫して呼吸困難などを引き起こします。
横隔膜ヘルニアは胃や内臓の位置が正常でないために、出生前の超音波検査で疑われることが多いのが特徴です。羊水多過であることも多いようです。その場合、精密超音波検査やMRIで重症度を確認します。
肺に嚢胞(のうほう)と呼ばれる袋状の病変ができる病気を「先天性肺嚢胞性腺腫様形成異常」と呼びます。先天性肺嚢胞性腺腫様形成異常(CCAM)と先天性肺気道奇形(CPAM)の違いは、嚢胞の大きさの分類や発生部位によって病理組織的に分類したかの違いによります。
妊娠5~6週目頃の肺形成に、何らかの異常が起きて発生すると言われ、胸腔内で嚢胞が心臓や正常肺を圧迫して胎児期や出生後にさまざまな問題を引き起こします。
出生前の精密超音波検査やMRI検査によって判明することが多く、羊水多過の場合も半数近くあります。
先天性肺嚢胞性腺腫様形成異常(CCAM)・先天性肺気道奇形(CPAM)をもっと詳しく
分娩・不妊治療・婦人科治療は扱わず、胎児診断を専門とする施設として2006年に開院。絨毛検査13,414件・羊水検査2,098件と、専門施設として実績豊富(2009年~2019年累計)。大学病院から紹介があるほど医療関係者から信頼が厚く、全国から妊婦さんが集まります。

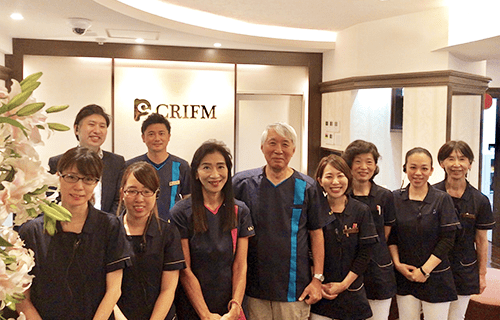
所在地:大阪府大阪市天王寺区上本町7-1-24松下ビル3F/問い合わせ:06-6775-8111
※開院年度・実績については同院HP参照