更新日:|登録日:
更新日:|登録日:
このページでは、水頭症の症状や出生前の診断方法、治療法などについてまとめています。
水頭症とは、何かしらの原因によって髄液の循環経路の流れが悪くなり、髄液が脳室に滞って脳室が拡大している状態を指します。拡大した脳室は、脳を内側から圧迫して頭蓋骨がまだ癒合していないために、脳圧が高くなると頭囲が大きくなってしまうのが特徴です。日本人の場合、先天的水頭症で生まれてくる確率は1,000人に2~3人となっています。
胎児期の水頭症は、出産前の検査で判明することが多いですが、注意が必要です。妊婦の超音波(エコー)診断で胎児水頭症が疑わしいと判断された場合、専門家がいる施設で、神経超音波検査やMRI検査をすることが勧められます。妊娠18~20週くらいで水頭症の疑いがあっても、自然に治ることもあります。また、水頭症の原因もいろいろあるので、きちんと専門家に調べてもらいましょう。
水頭症を起こす原因には、髄液の生産過剰や髄液循環路の閉鎖、髄液の吸収障害などが考えられます。
胎児や出生直後の新生児の場合は、先天性水頭症と診断されます。頻度の高いものでは、腰部や仙骨部の皮膚欠損や腫瘤を認める「脊髄髄膜瘤」や「脊髄披裂」によるもの、あるいは髄液循環を妨げる「中脳水道狭窄症」による水頭症です。これらは物理的に水がとおりにくくなる部分があるので水頭症になり、脳神経自体の異常というわけではありません。
しかし、先天性水頭症には、遺伝子の異常によるものも多く認められており、現在では100個以上の遺伝子変異が確認されています。遺伝子変異による水頭症の場合には予後がよくないことが多く、遺伝子変異がないかどうかは予後の大きな決め手となることもあります。
水頭症はあくまでも「状態」のことを言い、その原因や水頭症によって起こされる疾患によって生まれた後の神経予後や治療方針が変わってきます。
脳脊髄液(髄液)は脳室で産生され、その後脳や脊髄のまわりを循環して、脳や脊髄実質の非常に細い毛細血管やくも膜顆粒から吸収されると考えられています。ヒトの脳は髄液に浮いています。水が入っている真空パックのお豆腐はパック内で潰れませんね。これと同じで、脳も髄液の中で浮いていて傷つかないようにできています。
水頭症は、何かしらの原因によって髄液の循環経路の流れが悪くなり、脳室に滞ってしまうことで脳室が拡大している状態のこと。水頭症の原因が何かによって、さまざまな症状があらわれます。
水頭症が起こる原因によって異なりますが、新生児や乳児の場合は頭囲の拡大、嘔吐、睡眠時間が長い、情緒不安定、前頭部の突出などの症状が見られます。またてんかんや痙攣がでることもあり、幼児以降の場合は、頭痛や嘔吐、眼球の神経麻痺、筋肉や腱の収縮や弛緩などの症状が見られこともあります。
水頭症を引き起こしている原因により治療方法は異なります。先天性の場合は、脳脊髄液の循環経路に異常がみられるケースが多いため、たまり過ぎた髄液を抜く治療を実施します。
新生児の場合、赤ちゃんの全身状態や体重で初期治療の進め方を決定します。一般には出生後に髄液リザーバーを頭皮下に設置して定期的に髄液を穿刺して排液する方法か、脳室にチューブを入れて髄液をお腹へ流すシャント手術を行います。赤ちゃんが少し成長してから神経内視鏡を使って脳室に穴を開けてくも膜下腔と交通させる第3脳室穿破術という方法をとる場合もあります。
水頭症はこのような形で治療を行うことはでき、多くの場合はシャントをずっと留置することで症状が消失していきます。
妊娠中の検診で、お腹の赤ちゃんが水頭症の疑いが高いと診断された場合でも、医師による的確な娩出時期や娩出方法を示すエビデンスはまだありません。
ただ、進行性水頭症で頭蓋拡大が見られる場合でも、肺の成熟をできるだけ待ってから分娩するのが望ましいでしょう。状況によっては、帝王切開になる場合もあります。
妊婦さんやその家族、出生後の治療を担当する新生児科や小児神経外科などと連携を取り合いながら対策を考えます。妊婦さんと胎児の症状、状態に応じて、最善の分娩時期や方法を選択することになるのです。
出生前診断とひとくちに言っても、クリニックによっては検査項目が異なるほか、医師の専門分野によっても診断できる範囲が変わってきます。
当サイトを監修してくださっている「クリフム出生前診断クリニック」では、胎児脳の権威である夫律子院長がお腹の赤ちゃんの頭部や脳を詳しく検査しています。
夫院長はこれまで多数の論文を発表されており、胎児脳に関する書籍も海外で3冊出版されるなど、お腹の赤ちゃんの脳を25年以上診てきた産婦人科医です。2019年には、クリニックがあるビル4階に「胎児脳センター」という名前の専用フロアを設け、胎児の脳ドックを提供しています。超音波検査を補完する画像検査として、梅田脳・脊髄・神経クリニックと提携してMRI検査も実施しているようです。
お腹の赤ちゃんの頭部や脳のことで心配なことがあれば、ぜひ相談してみてください。

クリフム出生前診断クリニックの院長である夫律子先生が、4万人以上の胎児を診てきた中で9組の家族の物語をまとめた1冊です。
出生前診断が「命の選別」や「ダウン症を診断するための検査」という誤解が広まる一方、胎児と向き合う現場からのリアルなメッセージが詰まっています。
分娩・不妊治療・婦人科治療は扱わず、胎児診断を専門とする施設として2006年に開院。絨毛検査13,414件・羊水検査2,098件と、専門施設として実績豊富(2009年~2019年累計)。大学病院から紹介があるほど医療関係者から信頼が厚く、全国から妊婦さんが集まります。

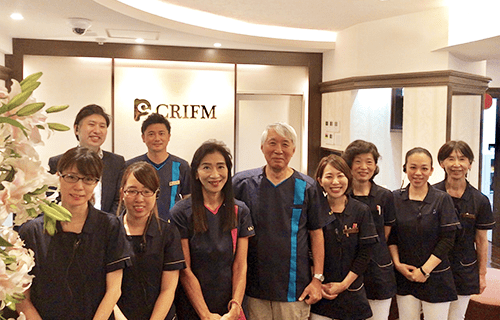
所在地:大阪府大阪市天王寺区上本町7-1-24松下ビル3F/問い合わせ:06-6775-8111
※開院年度・実績については同院HP参照
脳室が拡大しているからといって「水頭症」という名前で片付けられる訳ではありません。
脳室が大きい場合には一般に脳室三角部を測って、10mm以上の場合は脳室拡大と言われることがあります。10-12mmの場合は軽度、13-15mmの場合には中等度、15mmを超える場合には重度と判定されますが、比較的予後が良いとされる脳梁欠損などによる脳室拡大の場合には15mmを超えても神経学的にとても予後が良いことがあります。
ですから、ただ、計測値だけで早計に判断することはよくありません。何度もいいますが、脳室が拡大している場合にはその原因を調べることが大切です。脳室が拡大しているだけでは病気とは言えません。髄液の流れが悪いだけなのか、大脳の発育が悪いからか、遺伝子の病気がないのか、などきちんと調べることが大切です。
また、妊娠中に脳室拡大があっても自然に治ってしまって何も症状なく、元気に育つ子供さんもおられます。
「クリフムの胎児脳センター」では、脳室拡大の赤ちゃんを最低3回連続で詳しい脳神経超音波を行なって検査をし、いろいろな部位をしっかり見て診断をつけていきます。クリフムオリジナルの脳観察と遺伝子などの検査により、原因を確認してママパパと一緒に大切な赤ちゃんのことを考えていきます。
≫夫律子先生ってどんな人?
インタビューを見る
夫 律子(ぷぅ りつこ)
クリフム出生前診断クリニック 院長(日本産科婦人科学会認定産婦人科専門医/日本超音波医学会認定超音波専門医/日本人類遺伝学会・日本遺伝カウンセリング学会認定 臨床遺伝専門医ほか)
≫監修者情報を詳しく