更新日:|登録日:
更新日:|登録日:
こちらのページでは、生まれつきの肺疾患である先天性肺嚢胞性腺腫様形成異常(CCAM)の特徴や発症理由、治療法についてまとめています。
先天性肺嚢胞性腺腫様形成異常とは、生まれつき肺に嚢胞(のうほう)と呼ばれる袋状の病変が多数できてしまう病気です。英語の名称を略してCCAM(Congenital Cystic Adenomatoid Malformation)と呼ばれることもあります。先天性嚢胞性腺腫様奇形(CCAM)は嚢胞のサイズにより3型に分類されてきていましたが、近年、先天性肺気道奇形(CPAM:Congenital Pulmonary Airway Malformation)という病理組織学的に発生部位を考慮した新分類(5型)が推奨されてきています。ここではかつてからの分類のCCAMという言葉を使っています。
生まれる前に妊婦健診の超音波検査で発見されるケースと、生後まもなく発熱や咳、肺炎などの症状を発症することで、レントゲンやCT検査でわかることがあります。
妊婦健診の超音波検査で、先天性肺嚢胞性腺腫様形成異常の疑いがあると診断された場合、さらに詳しい症状を知るためにMRI検査を行います。
赤ちゃんは出産直後から肺で呼吸を始めますが、その際に肺の嚢胞が正常な肺を圧迫してチアノーゼをともなう呼吸困難を起こす恐れがあります。MRIで嚢胞の状態を確認して、生後に緊急手術が必要かを判断する必要があるのです。
その一方で、一度先天性嚢胞性肺疾患と診断されたとしても、妊娠後半に嚢胞が少しずつ縮小して消失していくケースも多く報告されています。嚢胞の経過を観察するためにも、定期的に検査を継続します。
先天性肺嚢胞性腺腫様形成異常は、妊娠5~6週目頃に肺が形成する過程において、発生異常が起きて嚢胞が作られると考えられています。病変の種類や異常の起こる発生段階など、まだ不明点が多いのも事実です。
先天性肺嚢胞性腺腫様形成異常は、妊娠2カ月頃に何らかの要因で肺の形成異常が起こり、多数の嚢胞ができてしまう先天性の疾患です。お腹の中の胎児が大きくなる過程で、嚢胞が小さくなるケースもありますが、嚢胞が大きくなって他の病気(胎児水腫など)と合併することもあります。
また先天性肺嚢胞性腺腫様形成異常の多くは、片側の肺だけに発生するのも特徴です。
肺の嚢胞が小さなうちは無症状ですが、出生後、肺呼吸に切り替わって一気に膨らむ可能性があります。そうなると、大きくなった嚢胞が正常部の肺を圧迫して、呼吸不全や呼吸障害に陥ります。
さらに嚢胞は、細菌に感染しやすいために、肺炎になりやすいのも特徴です。咳や発熱、痰、呼吸困難といった症状を繰り返すことになります。正常な肺機能を取り戻すために、乳幼児期に外科的切除を実施するのが一般的です。手術をせずに放置すると、呼吸障害が続くだけでなく悪性腫瘍になる可能性も示唆されています。
先天性肺嚢胞性腺腫様形成異常で生まれてきた赤ちゃんは、乳児期から幼児期初期までに病変を切除する手術が行われるのが一般的です。赤ちゃんの症状が安定している場合は、生後6カ月頃までにすると肺炎の発症リスクを抑えることができます。
胎児MRIなどを観察して、緊急性の高いものは出産後すぐに手術を行う場合もあります。
原則的に外科手術はすべての嚢胞の切除を目指しますが、嚢胞の範囲がはっきりしない場合や、残る肺が小さくなりすぎてしまう場合は、嚢胞の一部を残す場合も。その後の経過をみて再手術を検討します。
症状によって抗感染治療や呼吸補助、胸腔ドレナージなどの療法も実施します。
分娩・不妊治療・婦人科治療は扱わず、胎児診断を専門とする施設として2006年に開院。絨毛検査13,414件・羊水検査2,098件と、専門施設として実績豊富(2009年~2019年累計)。大学病院から紹介があるほど医療関係者から信頼が厚く、全国から妊婦さんが集まります。

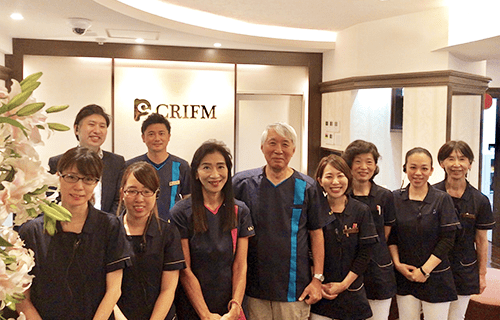
所在地:大阪府大阪市天王寺区上本町7-1-24松下ビル3F/問い合わせ:06-6775-8111
※開院年度・実績については同院HP参照
CCAM(CPAM)は妊娠20週前後に超音波で心臓の位置が普通と違うなどの所見で紹介されてくることが多いです。正常肺がどれくらいあるかということも重要ですが、妊娠中に病変がどんどん小さくなってなくなっていく症例も多く経験しています。胸に病変があると言われるととても心配になりますが、赤ちゃんの力を信じて見守ってあげることも大切です。
≫夫律子先生ってどんな人?
インタビューを見る
夫 律子(ぷぅ りつこ)
クリフム出生前診断クリニック 院長(日本産科婦人科学会認定産婦人科専門医/日本超音波医学会認定超音波専門医/日本人類遺伝学会・日本遺伝カウンセリング学会認定 臨床遺伝専門医ほか)
≫監修者情報を詳しく