更新日:|登録日:
更新日:|登録日:
このページでは、頭部や脳の形成異常や疾患の症状、出生前診断の方法や治療法について、クリフム出生前診断クリニックの院長・夫律子先生の監修のもと、解説しています。
妊婦健診の中に、超音波(エコー)検査があります。通院しているクリニックによって超音波検査の回数は異なりますが、とくに問題がないようであれば妊娠初期~23週の間に2回、24週~35週の間に1回、36週以降で1回が標準的(※)です。
ただ、妊婦健診で行われる超音波検査は「一般超音波検査」といって、羊水量や胎盤の位置、胎動を確認したり発育を評価したりなど、検査項目は限られています。
一方、出生前診断で行われる超音波検査は「精密超音波検査」といい、先天的な異常がないか、一般超音波検査よりも細かくお腹の赤ちゃんを診ていくものです。
頭部や脳に関しては、主に次のような項目についてチェックしています。
このような項目を1つずつ丁寧に確認して、脳や頭蓋の異常の有無を診ていきます。ただし超音波検査時の胎児の位置や向き、子宮内の状況にもよるので、すべての脳や頭部の異常が精密超音波検査でわかるとは限りません。
クリフム出生前診断クリニック胎児脳センターのように胎児脳ドックを詳しく行なっている施設では、もっと多くの項目について検査しています。
※参照元:[PDF]厚生労働省「妊婦健診」
妊婦健診の超音波検査で頭部や脳の異常が疑われる場合、さらに詳しい検査が必要になります。さらに明瞭な画像がわかる精度の高い機器や、画像解読に優れた医師による精密超音波検査(脳神経超音波検査という高周波経腟3D超音波検査を使った方法)や、胎児MRI検査で診断していきます。とくにMRIは、妊娠後半期の中枢神経系(脳や脊髄)の画像診断に有効です。
頭蓋縫合(ずがいほうごう)とは、主に5つのピースに分かれている頭蓋骨のつなぎ目の部分を言います。出生後も大きくなる脳の成長に対応できるように、頭蓋骨の骨片の癒合はゆるやかに進行しますが、胎児期には頭蓋骨はバラバラの状態のままです。頭蓋骨縫合早期癒合症は、お母さんのお腹の中にいるうちに頭蓋骨の一部が癒合してしまう病気です。
一度縫合した部分の頭蓋骨拡大は起こらないため、赤ちゃんの成長とともに頭蓋骨や顔面の形がいびつになるなど、脳組織の正常な発達に影響を及ぼします。
頭蓋骨縫合早期癒合症には、赤ちゃんの身体のなかで頭蓋だけが癒合する単純性のタイプと、顔面や手足の異常をともなうタイプの症状があり遺伝子変異による先天性の病気です。
頭蓋骨縫合早期癒合症は、特徴的な頭の形や顔の形をしているので妊婦健診の超音波検査で疑われることがありますが、一部の早期癒合の場合には見つからないことも多いです。その後、確定的な診断をするために胎児CTやMRIなどを用いて骨の縫合部分や脳の検査を実施します。
頭蓋骨縫合早期癒合症の治療は、狭くなった頭蓋を拡大して脳が成長できる環境と、頭の形を整えるための手術をします。通常は生後1歳以下で行いますが、その他の緊急性のある合併症を伴う場合は、さらに早い時期に手術を行うこともあります。
全前脳胞症とは、妊娠超初期に左右の大脳半球(前脳)が分離不全を起こす症状のことです。前脳の分離障害によって生じるものですが、はっきりとした原因はわかっていません。分離障害の程度により無分葉型・半分葉型・分葉型の3つのタイプがあります。13トリソミーや18トリソミーなどの染色体異常に併発する例やその他の微細染色体異常や遺伝子変異によるものもあります。
約8割の赤ちゃんに眼窩狭小や単眼症、鼻中隔欠損、鼻の位置異常、単鼻腔、口唇・口蓋裂など顔面に形成異常があり、知能障害や運動障害、その他視床下部・下垂体・脳幹機能による低体温・呼吸不全・摂食障害を起こすことがあります。1万人に対して1人の割合で生まれてくる稀な疾患ですが、出生まで至らず自然流産になるケースも少なくありません。
妊婦健診の一般超音波検査で頭が小さい、脳の正中線が見えないなどということからわかることがあります。精密超音波検査で顔面異常を含めて診断されることが多いです。疑わしい場合には、染色体検査や遺伝子検査をする場合もあります。
全前脳胞症の症状には個人差がありますが、多くはかなりの介助が必要となります。とくに無分葉型・半分葉型では全ての生活でほぼ全介助となることが多いです。内分泌障害の治療や発達障害に対するリハビリ、呼吸や循環不全の管理と治療などが実施されます。
脳梁欠損症(のうりょうけっそんしょう)とは、左右の大脳をつなぐ脳梁という神経束が欠損している状態を言います。脳梁とは、左脳と右脳をつなぐ2億本以上の神経繊維束のことで、互いの脳の情報を交換する役割を持つ部位のことです。
脳梁欠損があっても左右の脳はその他のところでうまく連携をとっていますので、全く症状がないことも非常に多いです。大人になってたまたま交通事故に遭ってMRIを撮ったら脳梁欠損が見つかったと言う人もいます。
脳梁欠損症は、脳梁が形成される妊娠16週頃までに、何らかの要因によって起こるとされていますが、原因は分かっていません。
脳梁欠損単独の場合は上述のようにまったく神経障害などがなく普通に育っていくことがおおいのですが、その他の脳形成障害や症候群などを合併している場合には神経障害が起こる可能性が高くなります。
脳梁欠損症の場合、脳室の後ろの方が大きくなるため、妊婦健診の超音波検診で脳室拡大が疑われてわかる場合もありますが、脳梁自体は妊婦健診の超音波検査では確認されません。
脳梁は妊娠18週以降で確認されるので、胎児脳ドックなどでチェックすることができます。脳梁欠損を合併する症候群などもあるため脳梁欠損がある場合には精密に脳全体のチェックをすることが望ましいです。
「脳梁欠損症=病気」という定義づけはされていませんが、脳構造が少し違う形をしているので、小児神経科の専門医に診てもらってフォローしてもらうほうがいいでしょう。
小脳低形成は、比較的稀な中枢神経の異常で、小脳の半球が低形成だったり、虫部(正中部)が低形成だったり欠損している状態のことです。とくに虫部の形成がゆっくりしている症例は意外によくみられますが、生まれてから全く問題なく育っている方も多いです。小脳全体の低形成は18トリソミーなどの染色体異常でもよくみられます。
虫部欠損の赤ちゃんの中には運動機能や知的発達に遅れがあることもあり、なかには視神経の障害や内臓機能、神経系機能に障害をもたらすジュベール症候群という遺伝子変異による重症の病気であることもあるため、詳しい脳ドックが必要です。
妊婦健診の超音波検査で判明することがあります。
現在のところ、根治的治療は困難であり、対症療法のみです。
神経細胞移動異常症とは、先天的な大脳皮質の形成異常による病理形態のことで、「滑脳症」や「異所性灰白質」「「多小脳回」などの総称です。現在では「大脳皮質形成異常」、英語ではMCD(Malformations of Cortical Development)と総称されることが多く、MCDは神経細胞移動障害だけでなく、神経細胞の増殖や、細胞移動後の障害も含まれます。
妊娠8週以降に胎児の脳で生じる神経細胞は、妊娠3~5ヶ月くらいに内側から外側に移動していき大脳皮質という大脳の表面の構造を形成していきますが、何らかの要因によって障害されることで大脳皮質に異常をきたします。
神経細胞移動異常症の一部の病態は、遺伝子変異やサイトメガロウイルス、染色体微細欠失によるものなどが原因とわかっています。
症状は個人差が大きく、難治性のてんかん発作や痙攣、知的障害、成長の遅れ、運動障害が起こることが知られており、小児神経科では大きな問題として取り上げられています。
神経細胞移動障害の結果、大脳にシワができないとか、シワができすぎる状態は妊娠後期にならないとわかりません。つまり、このような異常は妊娠30週をすぎないとわからないことがほとんどなのですが、一般の妊婦健診で診断されることはほとんどありません。妊婦健診で頭が小さい、あるいは頭が大きいと診断される赤ちゃんの中に、重症な大脳皮質形成異常の赤ちゃんがいることは確かです。
クリフム出生前診断クリニックの胎児脳ドックでは、妊娠18~20週くらいで神経細胞移動障害を見つけることにおいて世界でもトップクラスの研究をされていますが、それでもすべての脳障害がこの時期にわかるわけではありません。
現在のところ、根本的治療法はなく対症療法のみです。患者さんの症状に応じて抗痙攣薬の服用やリハビリテーションなどをしていきます。
無頭蓋症とは、生まれつき頭蓋骨が部分的、または全体的に欠損していることです。そして無脳症とは、大脳の一部、または全体的に欠損が見られる状態のこと。妊娠超初期にできる神経管は早期に閉鎖していきますが、何らかの原因でこの閉鎖が頭の先だけおこらないこと(閉鎖不全)で、頭の皮膚や頭蓋骨がうまく形成されないと言われています。
無頭蓋症の赤ちゃんでは脳は作られていますが、頭蓋骨がないため、脳が羊水腔にむき出しになっており、赤ちゃんが動いて頭をぶつけることでその脳が破壊されてしまい、無脳症となります。そのため、無脳症と無頭蓋症は「一連の病態」と考えられています。
妊婦健診の超音波検査の画像で、赤ちゃんの頭に丸みがなかったり、頭の一部が映らなかったりして判明するケースが多く見られます。
脳の周りを覆っている「くも膜」に嚢胞(のうほう:水たまり)ができる病変を「くも膜嚢胞」と呼びます。嚢胞の中身は髄液なので悪性ではありませんが、くも膜嚢胞はどこにでもできるため、大きさによっては脳や脳幹を圧迫するために治療が必要となる場合があります。
生まれる前の妊婦健診で判明する割合は低く、生後もとくに痛みなどの症状が出ないことが多いようです。また妊娠中に小さくなったり大きくなったりすることもあり、生まれてからも同じです。出生後に別件で撮ったMRIなどで判明することもあるとされています。高度な超音波機器を用いる精密超音波検査を実施した場合は、胎児期にくも膜嚢胞と診断がされるケースがあります。
頭蓋骨の形成が正常にされなかったことで欠損部が生じ、そこから髄膜や脳脊髄液、脳組織が飛び出している状態を呼びます。髄膜や脳脊髄液だけのものを「髄膜瘤」、脳組織が含まれているのを「髄膜脳瘤」と呼びます。
妊娠初期の神経管形成時には神経管閉鎖はほぼきちんと行われ、その後、頭蓋骨が出来ていく過程で何らかの原因で頭蓋骨の一部欠損が生じると言われています。妊婦健診の超音波検査で疑わしいと診断されることがあり、専門家による精密超音波検査やMRI検査で診断されます。
水頭症とは、髄液の生産過剰や髄液循環路の閉鎖などによって髄液が脳室に滞ってしまうことで、脳室が拡大している状態のことです。水頭症はあくまでも「状態」のことで、その原因となる脊髄髄膜瘤や脊髄披裂、中脳水道狭窄症などの原因となる疾患で起こるため、治療方針もその病気によって変わります。
水頭症と似た状況ですが、髄液循環路は正常である「脳室拡大」の状況もあります。脳室拡大、水頭症、いずれも原因が重要です。ダウン症その他の染色体異常や遺伝子変異、大脳発達不全などで起こる場合もあり、精密な脳ドックを受けることが勧められます。
水頭症は妊婦健診の超音波診断で疑わしいと判断されることが多く、その場合は胎児脳ドックなどさらに詳しく調べて診断を確定します。
分娩・不妊治療・婦人科治療は扱わず、胎児診断を専門とする施設として2006年に開院。絨毛検査13,414件・羊水検査2,098件と、専門施設として実績豊富(2009年~2019年累計)。大学病院から紹介があるほど医療関係者から信頼が厚く、全国から妊婦さんが集まります。

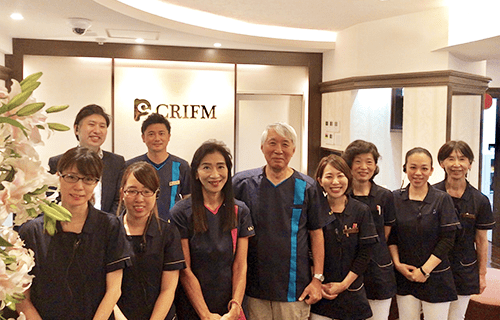
所在地:大阪府大阪市天王寺区上本町7-1-24松下ビル3F/問い合わせ:06-6775-8111
※開院年度・実績については同院HP参照
胎児の脳診断は非常に難しいです。私は、胎児脳診断を20年以上専門にやってきており、胎児脳ドックを行なっていますが、まだまだ分かっていないこともあります。
一般の産婦人科では赤ちゃんの頭の中に水がたくさん溜まっている状況の時のみ「水頭症」という診断をして、「生まれてからのシャント手術」で治りますと説明されていることもよくありますが、実際にはそう単純なものではありません。頭に目立った水溜りなどがないけれど非常に重症な脳障害となるような疾患はほとんど妊婦健診では見つからず、また生まれてからも症状が出るまで診断されず放置されることがほとんどです。もちろん自閉症などはどんなに検査しても形態ではわかりませんが、先天異常に基づく脳異常は脳ドックでわかることが多いです。
胎児脳ドックをおこなっている施設はまだ多くありませんが、きちんと脳の精密検査を受けておかれると安心ですね。
≫夫律子先生ってどんな人?
インタビューを見る
夫 律子(ぷぅ りつこ)
クリフム出生前診断クリニック 院長(日本産科婦人科学会認定産婦人科専門医/日本超音波医学会認定超音波専門医/日本人類遺伝学会・日本遺伝カウンセリング学会認定 臨床遺伝専門医ほか)
≫監修者情報を詳しく